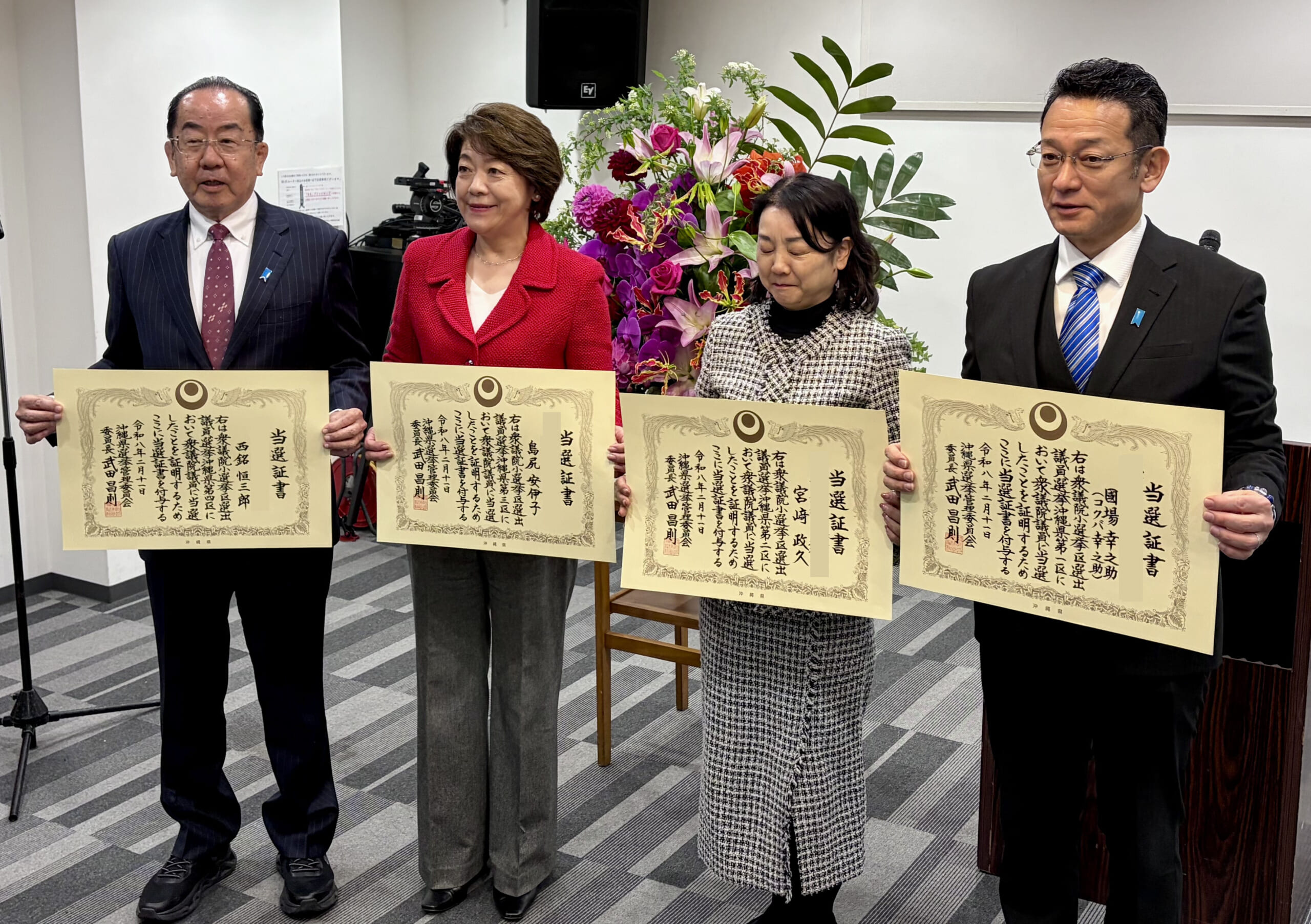「バスケコートを社会課題解決の場に」 インディペンデンス社長、近藤洋介氏が語るそのココロ!強豪チーム再生からの信念

バスケットボールを愛するあまり、老舗洋和菓子店の家業をなげうち、「バスケコート屋さん」に転身した。レンタルコート「ディーナゲッツ」を手掛けるインディペンデンス社長、近藤洋介氏(52)のめざすところは「バスケットコートを街のコミュニティセンターに」。コートを人々の交流の場に発展させ、「子供の居場所確保」「世代間交流」を通じて社会課題の解決に結びつけていこうという取り組みだ。一方で、低迷したチームの「再建請負人」の顔も合わせ持つ。
■沖縄にビジネスチャンス
愛知県に本社を置く大正5年(1916年)創業の和菓子屋の三代目です。続けていれば100年超えるお菓子屋さん。祖父が和菓子を創業。父が洋菓子に転換して、私は結果的に洋菓子の看板を降ろして、バスケットに転身したわけです。
父は愛知県下にケーキ店を50店舗持ちながら、主力事業は愛知、東京、大阪でホテルの結婚式に引き出物を納入する仕事でした。ですが私が米国バスケ留学から帰国し、家業を継いだ1995年ごろには結婚式が小型化し、レストランウェディングやリゾートウェディングが主流でした。それで、この3拠点でだけで仕事をしていても広がらない、地方都市を攻めようと、営業拠点を札幌から沖縄までいきなり16カ所に増やしました。私の出身高校は進学校で、アメリカへのバスケ留学を実現する為に、父と帰国したら家業を継ぐと約束していたし、自分でもそのつもりで頑張ったのです。
沖縄は歴史的な背景もありアメリカ文化が根強く、バスケがとても盛んです。私もバスケと関わってきたので、その時の支店長さんと「沖縄にクラブチーム作りたいね。ウチのブランドをユニフォームの胸に入れて」なんて話をしていました。
■キングスとの出会い
沖縄では、結婚式の前に結納式があります。これが当時の東京の結婚式ぐらいの規模。50人から70人ぐらいが結納式に集まり、披露宴となると、300人、400人。ですから、引き出物が東京だと20、30個なのに、沖縄だと300個とかになるので、営業の力の入れ方も変わります。私が沖縄の営業所に行く頻度も上がって、ホテルをどんどん開拓をしていきました。一時は沖縄の結婚式の引き出物のシェア、70%もいったかな。そのころです。支店長がファクスを本社に送ってきた。地元紙の記事(2006年3月2日付)で沖縄にプロバスケチームができると。すぐに支店長を通じて連絡を取り、立ち上げようとした人に会えたのですが、私の人生がドラスティックに変わるきっかけでした。
 (左)琉球ゴールデンキングス共同創業者 兼 初代社長 木村達郎氏
(左)琉球ゴールデンキングス共同創業者 兼 初代社長 木村達郎氏
その人は、後に琉球ゴールデンキングス社長になる木村達郎さん。たまたま同い年で、同時期にアメリカにいたことがわかり初対面だったのですが打ち解けて、いい関係ができました。キングスのbjリーグ参入記者会見にも呼ばれ、コミッショナーの河内敏光さんにも紹介していただきました。その後のキングスの歩みは私が説明するまでもなく、今や日本を代表するプロバスケチームです。私はキングスの初期株主となり、以後、沖縄をはじめバスケットと関わっていくことになり、人生が180度変わりました。
■レンタルコート事業開始
キングスが発足した2007年、レンタルバスケットボールコートを地元の愛知県一宮市で始めました。地域の人が世代を超えて、いつでも好きな時にときに、誰でもプレーできるように、という思いからです。これは、河内敏光(現在は当社会長)さんとのご縁をいただき、bjリーグの事務所にお邪魔したときに、「これからチームがどんどん増えてバスケットの裾野が広がっていくでしょう。大勢がプレーできるコートを増やしてほしいです」とお願いすると、「それは近藤さんがやったらいいでしょう」と背中を押されてスタートしました。その後、このレンタルコートはどんどん増えて、今は全国で9カ所です。※1(愛知、北海道、伊丹エアポート、トレッサ横浜、名古屋、沖縄コザ、八重瀬、国際通り、那覇空港)
 (左)小学生時代の富永啓生選手
(左)小学生時代の富永啓生選手
レンタルコート1号店であるディーナゲッツ愛知に8歳の時から通ってくれていた選手の一人が、東京2020、ワールドカップ2023、パリ2024、アジアカップ2025の日本代表として活躍している富永啓生選手。幼少期からのご家族を含めたお付き合い(お父様が同い年)があり、富永選手がネブラスカ大学でプレーし始めた頃からサポーターとして関わり、大学卒業と同時にマネジメント契約を締結。彼の現役と引退後を見据えたアフターキャリアまでをサポート、応援させていただいています。
今ディーナゲッツに通っている子供たちが憧れ、そして目指す素晴らしいモデルケースとして大活躍してくれており、また富永選手もいつもディーナゲッツと子供たちを気にかけてくれています。
 (左)富永啓生選手@ディーナゲッツ愛知
(左)富永啓生選手@ディーナゲッツ愛知
沖縄にはキッズ専用のコートを常設型・仮設型を含めて4カ所設置しています。キングスが生まれ、沖縄アリーナができてトップレベルの形は整いました。そこで、以前キングスが沖縄全域でやっていたような草の根的な活動をして、沖縄の皆さんにも喜んでいただきたいと考えました。私は沖縄のおかげでキングスに携わり、お菓子屋さんから転身するきっかけになった。だから恩返しです。そこで始めたのが小さな子ども専用のコート。冷房がついていて、大きいお兄ちゃんが来ない、小学生以下の子どもたちが好きなときにバスケットができる。もしくは体が動かせるような場所を作ろうと。2021年10月、沖縄1号店を沖縄コザに開業しました。転んでも危なくないから、安心です。付き添ってくるお母さんたちにも安心して見ていただける。※2(沖縄コザ、八重瀬、国際通り、那覇空港)
家業は、父がバブル経済に乗じた超多角化経営につまづき、153億円の借金ができていました。
私が売るものを処分して、がむしゃらに働いて、多くの方のお力添えをいただいて、あらゆる金融スキームを駆使して再建し、2007年に売却しました。借金の返済も終わり、今はバスケットに全身全霊注げるようになって、拡大路線に入っています。
■コートは「街のコミュニティセンター」
私はプレイヤーとしてアメリカ留学したのですが、プレーを諦めたとき、人が集まるアリーナに興味を持って、全米を見て回りました。そこで気づいたのは、日本なら、例えばジャイアンツとドラゴンズの野球のチケットを買ったら、早くスタジアムに入ってトイレも行かずに1回表から9回の裏まで全部見る、ってところありますよね。アメリカで衝撃だったのは、バスケットで第1クォーター始まっても、人が入ってこない。第2クォーターになって、だんだん入ってくる。ハーフタイムになるといなくなって、ゲームの終わりごろ、また来る。ハーフタイムにコンコースへ出て、バーがあったのでのぞいてみたら、大勢いる。「ゲームが始まっているのに、どうして中に入らないのですか」と聞いてみると、「バスケット見に来ただけじゃない。人に会いに来たんだ。だから、こうやって集まる。ゲームはそこにあるテレビで見ればいいだろう」と。ハンマーで頭を殴られたような気持ちになりました。
スポーツを観る場所というのは、人が集う場所なんだ、スポーツを中心に、「初めまして」とか、「久しぶりだね」っていう憩いの場なんだと学びました。接待に来ているビジネスマンがいれば、ビールを飲んでいるお父さんの横に、ポップコーンをかじっている子どもがいる。人々のあらゆるシーンがアリーナの中で繰り広げられるわけですね。そこで、私はアリーナは建てられないけれど、バスケコートを用意できれば、バスケをやる人も、やらない人も集まって来てくれる憩いの場所を作れるだろうと。これが、現代版の「街のコミュニティセンター」です。スタッフたちにも「公民館なるんだ。街のピースの一つになるんだ」と言い続けています。
■「バスカフェ」と呼ばれ、結婚式も
事業開始から18年。最近は「バスカフェ」と呼ばれるようにもなりました。ドリンクなども売っているので、バスケットコートがあるカフェだからです。最近は3パターンぐらいの光景を見ます。まずはピックアップゲームですね。1on1やろうよ、3on3やろうよとゲームが始まっていく。もう一つは自分より上手な人に、「ちょっと教えてください」と話しかけてシュートやドリブルを教えてもらったりしています。さらに、プレーはしないけどバスケ雑誌や漫画「SLAM DUNK」(スラムダンク)を読みに来たり、ゲーム機で対戦している子どももいますね。「バスカフェで集合」とか言って、宿題を持ってくる中高生もいて、見ていて微笑ましい光景です。コートで出会った男女が結婚したケースもあります。二次会はもちろんコートで開催されました。2年ほど、毎週のように孫を連れてきていた86歳のおじいちゃんは、元国体選手。昔のシューズをたんすから出して使っていました。さすがにお上手で、身のこなしも軽く、小学生たちから拍手喝采。おじいちゃん顔が立っていました。お客様一人ひとりにストーリーがありますね。
「マイファーストバスケットボールプロジェクト」という企画は、人生で初めてのスポーツがバスケという狙いで、2歳までの子を対象にしたのですが、お母さんたちの憩いの場にもなりました。子育ての相談から夫、舅への不満と話が弾んで、2時間ぐらいですっきりして帰っていかれます。子どもや母親の居場所確保につながり、社会課題の解決にも貢献できていると実感しています。
■運営を支えるコミュニティパートナー
レンタルコート事業の運営を支えるのは「コミュニティパートナー」制度です。コミュニティを一緒に作っていきませんか、という趣旨で企業から月1万円、3万円、5万円の会費をお預かりして、コートの運営資金に充てています。コートの時間貸しのレンタル料金は1人あたり数百円ですから大きい売り上げにはなりません。ほぼ無いに等しいので、会費で固定費を賄い、ボールを買うとか、アカデミーを開催した時の講師料になります。
パートナーの会費は、1万円ぐらいだったらいいよっていう企業が多いですね。月5万円以上を設定していないのは、大企業や余裕のある企業に多く出されると、パートナー間のバランスが崩れる恐れがあるからです。みんな同じ立ち位置でやってほしいのです。大企業だから、個人だから、ではなく同じ金額であれば、みんな同じ立ち位置で、同じ思いでやりましょうとなります。草の根的に、多くの企業に関わっていただきたいです。パートナー企業は現在72社です。地域的には65%が内地で35%が沖縄。これを300社まで拡大したいと思っていて、今は毎日営業活動をやっているところです。年12万円が300社で年間3600万円。これだけあれば、スタッフの人件費をはじめ、コートを増やしていく資金にもなるだろうと計画しています。
企業にはCSR(企業の社会的責任)、IR(投資家向け広報)、SDGs(持続可能な開発目標)といったものが求められる時代ですが、自社の特性を生かして社会貢献したいと考えている会社も多いです。最近、お話をいただいたのは、文具メーカーからキッズコートに絵を描くプロジェクトです。子どもたちとアーティストが絵を描いて、将来も残るようなコートを作る、街の風景を作ってとけこませていく。そういったさまざまな企業を巻き込んで支えてもらうことで、結果的にこの事業が大きくなると思っています。お金を回すことも考えなければいけませんが、究極的にはスポーツビジネスとは赤字にならなければいいと思っています。トントンでいいから、そこに関わる人、必要なものがちゃんと回り続けることが大事です。
■波照間島でも検討中
沖縄で事業をスタートして4年です。今もバスケットボールのレンタルコートの存在がよく知られているとは言えませんが、口コミによってじわじわ広がってきています。沖縄に来る前に各地で経験を積んできているので、お役に立てているんじゃないか、という自負はあります。いきなり沖縄に来てコートを作っていたら、多分できなかったでしょう。キッズアカデミーをやっているので、アカデミー生同士、お父さん、お母さんも仲良くなって、3on3のチームを作って町の大会出よう、みたいな動きが起き始めています。バスケの盛んな土地で、ワンコインで2時間、クーラーのある環境で安全に楽しめるというニーズは高いですね。
今後は沖縄の離島にも進出を考えています。いろいろ検討していますが、日本最南端の波照間島が有力です。なぜかというと、島には高校がない。ほとんどの子は高校入学のタイミングで石垣島か沖縄本島に出る。元気に出ていくけど、親元を離れる寂しさはありますよね。そこで年に1回でも大会を開けば、帰省する理由になるし、仕組みになる。島の子たちだけでなく、日本最南端の島でバスケをやろうとなれば話題性もあって全国から集まると期待できます。バスケって人を引き寄せる力がすごく強く、最高のコミュニティツールだと確信していますからぜひ実現させたい。石垣島、宮古島からは、お引き合いもあるので、タイミングをみて検討していきます。
波照間といえば黒糖ですね。家業の借金返済も終わったので、実はお菓子屋のリスタートも考えています。波照間産の黒糖をはじめ、沖縄の素晴らしい素材を使ってうまく加工すれば内地に広げられるかな、と思っていて、これをプラスアルファにしてバスケットに資金を投入できるようになればいいな、という構想です。
■チーム再生請負人の顔
2017年8月、群馬県の桐生第一高校から低迷していたバスケットボール部の再建を託されました。「再建できなければ廃部」と、崖っぷちに立たされてゼネラルマネージャーに就任し、「スポーツはコミュニティづくり」という私の信念に従って、復活させました。どういうことかというと、そこにいる人、関わる人を元気にしただけです。名門校に入部してくるぐらいだから、技術的な能力はとても高いレベルで、教えることなんかありません。では、なぜ勝てないか。選手たちは委縮していました。勝つことに圧をかけられ、指導者から暴言や暴力のような圧力も受けていた。私は選手たちに約束しました。決して殴ったり、怒鳴ったりしないと。選手たちは半信半疑のようでしたが、後に感謝されました。そして、なぜ、学校で暴力や暴言がなくならないのかを分析すると、先生たちが置かれた劣悪な就業環境が浮かびました。土曜、日曜も部活動を指導して、部活終わってから職員室に戻って、午前1時、2時までテストの採点とかをやっている。翌朝は6時に出勤する。まじめだから疲弊するんですね。
まず、こうした部活動の運営をいじって先生たちを少し休んでもらおうと週休2日にしました。ご家族とゆっくり休んでください、出かけてくださいと奨励しました。子供たちも週休2日にして、練習は1日1時間半としました。残って自主練習は認めるけど、1時間に限定し、体育館を開放するのは2時間半だけにしました。それまでは毎日5時間もやっていましたから。そうしたら、半年で県大会準優勝です。そして先日の11月3日、このチームは高校バスケの最高峰大会である「ウインターカップ 群馬県予選」で優勝し、今年の夏のインターハイ、そして冬のウインターカップで群馬県代表の2冠に返り咲き、2018年2月から始まった同校バスケットボール部の再建は、7年10か月の月日を経て完了しました。やっぱり必要なのは笑顔、元気なんです。障害物があれば、それを外してあげるだけです。スポーツをやって、笑顔になればいいコミュニティができる。これは本業である、レンタルコート事業のコミュニティづくりに通じることなのです。
■八重山の子供たちにメッセージを
バスケットボールのみならず、スポーツは何かやった方がいいですよ。国内外問わず、いろいろな街の人と友達になれる。家庭の状況で続けられないことがあるかもしれない。でも、プレーするだけがスポーツじゃないので、応援することを続けていけば、そのスポーツに関わっていることになる。世界共通のツールを持っていることになります。
【近藤洋介】
1973年7月生まれ。滝高校(愛知)を卒業し、米コロラド大ボルダー校へバスケ留学。帰国後、家業の洋和菓子メーカーを経営。2007年2月~2009年9月、琉球ゴールデンキングス初期株主及びGM補佐。2008年に(株)インディペンデンス設立し、代表取締役社長就任。2010年12~2011年6月、観光庁スポーツ・ツーリズム推進連絡会議委員。2017年8月~2020年3月、桐生第一高校(群馬)男子バスケットボール部ゼネラルマネージャー、強化指定クラブマーケティング室長などを歴任。現在はバスケットボール日本代表、富永啓生選手のマネージャーを務めている。