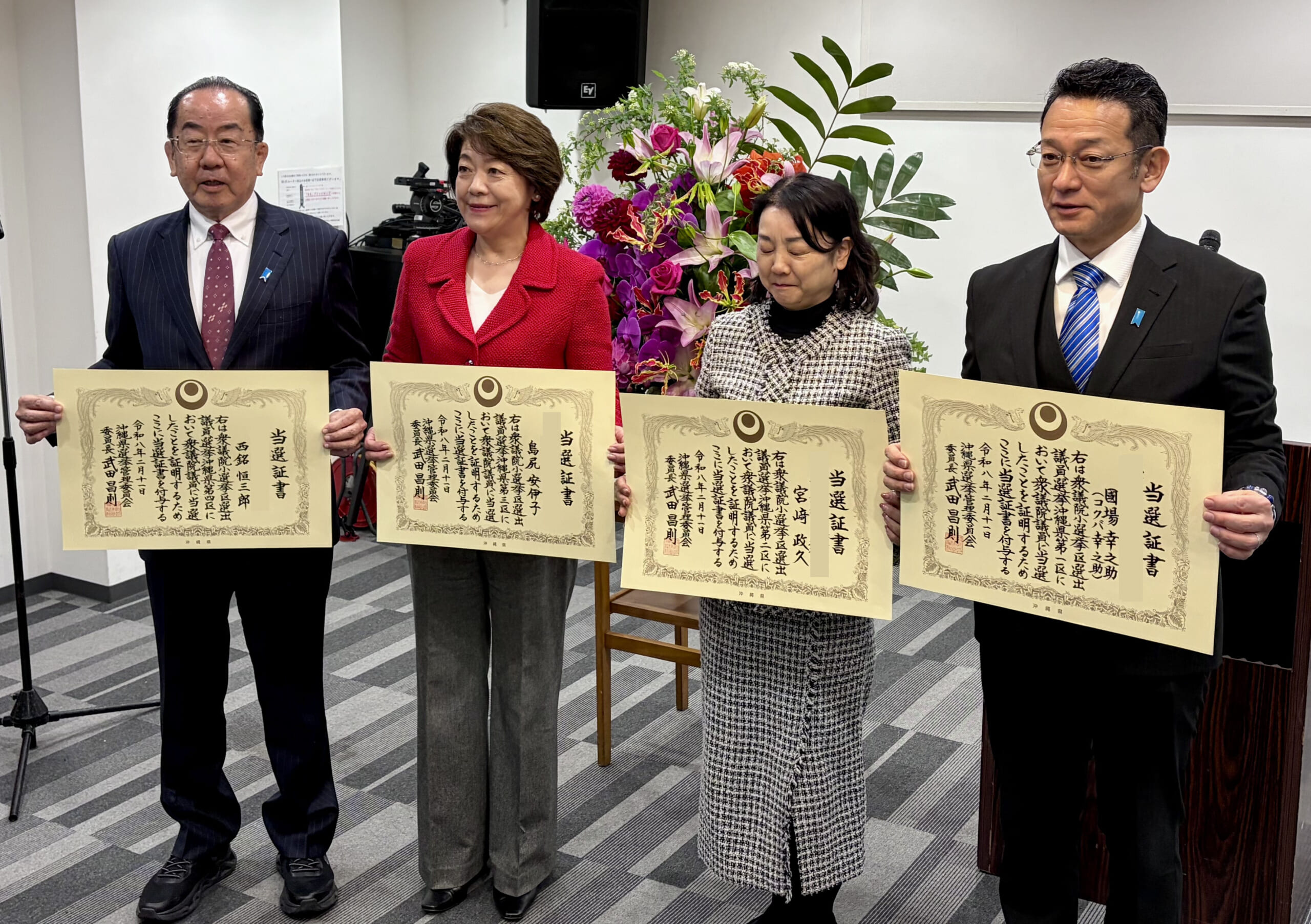【視点】成長戦略 離島にも恩恵を
国力の衰退に歯止めを掛けられるのか。高市早苗首相は今月開いた成長戦略本部と成長戦略会議で、AI(人工知能)・半導体や造船など17の戦略分野に集中投資する方針を示した。
各戦略分野に関し、政府が供給力強化や官民の投資ロードマップ作成などに取り組む。閣僚と有識者で構成される成長戦略会議で来夏の成長戦略策定を目指すが、近くまとめる経済総合対策では、ただちに実行すべき重点施策を盛り込む。
高市首相が特に重視するのは物価高対策、経済成長、防衛力と外交力の強化だ。
直近の課題はもちろん物価高対策であり、離島県である沖縄では輸送や移動のコスト増もあって、物価高の影響はとりわけ深刻である。
ガソリン暫定税率(1㍑当たり25・1円)が廃止されるが、沖縄の軽減措置(7円)も縮小される見通しで、この場合は暫定税率廃止後も沖縄のガソリン販売価格は全国ほど下がらない。ガソリン価格一つとっても、県民は全国でも何かと不利な状況に立たされている。
米価が高止まりしている問題では、政府は「おこめ券」の発行を検討しているという。物価高対策は一部の人だけに恩恵がとどまらないよう、離島の離島まで行き届く取り組みを期待したい。
経済成長の足かせになっているのが少子高齢化だ。政府は成長戦略の分野横断的な課題の一つに介護・育児の負担軽減や人材育成を盛り込んだ。
少子高齢化は人口減少を加速させ、需要の減少、労働力不足、他国との競争力低下などにとどまらず、社会全体の雰囲気を沈滞化させてしまう。国ぐるみでさびれた過疎地域に陥らないよう、成長戦略ではこの問題への対応を意識してほしい。
防衛力と外交力は一体だ。政府は戦略分野の一つに防衛産業を挙げた。防衛産業に使用される技術はデュアルユース(軍民両用)に対応するものが多く、生産基盤の強化は経済成長を促す効果も大きい。
大学によっては軍事研究を拒否しているところもあり、県内では琉球大もそうだが、軍民の技術を厳密に切り分ける意味が見いだせない。
防衛を米国に依存する現状を改める意義もある。日本の将来に防衛産業の基盤確立は欠かせない。
防災・国土強靭(きょうじん)化も成長戦略の柱の一つだ。将来来るべき災害の一つとして南海トラフ地震が取り沙汰されるが、沖縄でも八重山は津波の常襲地帯とされる。
1771年の明和の大津波から既に250年以上が経過する。いつ大災害が起きてもおかしくないリスクを抱える地域である。
高市首相は「危機管理投資・成長投資」の推進を掲げている。社会に蔓延する停滞感を打破するためにも、政策実行のスピード感が必要だ。